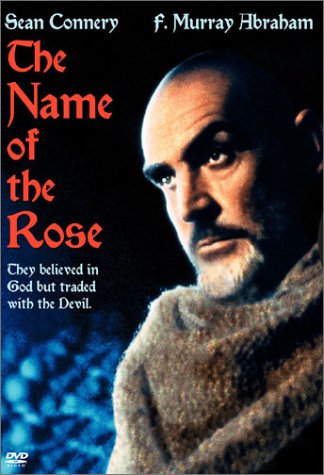We have developed speed, but we have shut ourselves in.
Machinery that gives abundance has left us in want.
Our knowledge has made us cynical; our cleverness, hard and unkind.
We think too much and feel too little.
--Chaplin. The Great Dictator.
(私たちはスピードを発達させてきたが、かえってその中に自らを閉じ込めてしまった。
豊かさをもたらしてくれる機械が私たちを欠乏に突き落としている。
知識のために私たちは皮肉屋になり、利口になった分、非情で冷酷になっている。
私たちは考えすぎて感じることがあまりに少ない。)

チャップリンの映画『独裁者 』の最後の演説の一部である。こういった対照法(antithesis)はポウプに頼めば手際よく処理してくれるかもしれないが、それではこの表現の直接性が失われるかもしれない。
初上映から65年。まったく色褪せていないことにむしろ驚かされる。いや、ますます現実味、そして凄みすら帯びてきている。いまこそ、チャップリンなのではないだろうか。