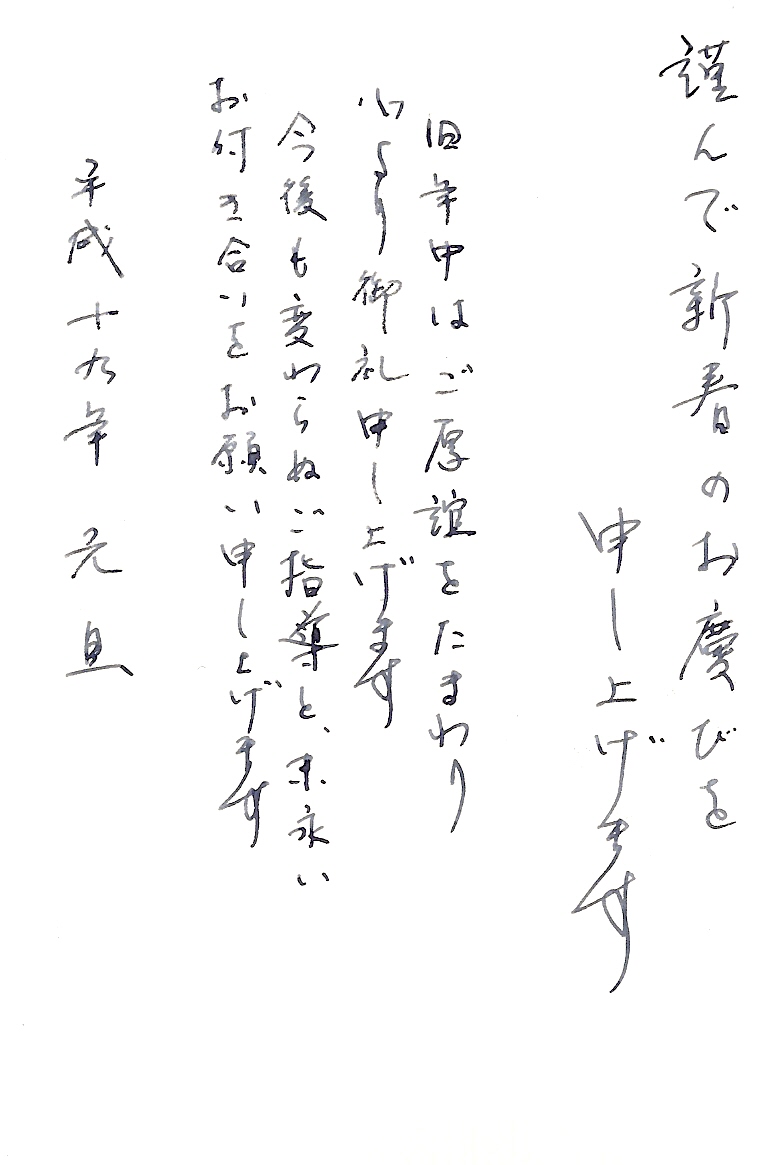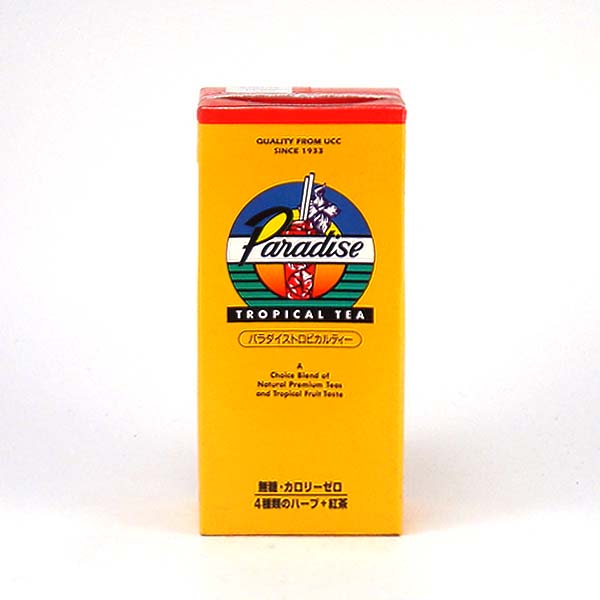生涯で一番楽しいカラオケはもう決まっています。前は難波、今は近江のジャズドラマーと行ったカラオケ。私は一曲も歌っていないんですがね。どういうことだって?
まず確認しておきたいのだけれど、私はカラオケが嫌いです。いや、むしろ懐疑的です。年に二三度は行くけれど、それは付き合いで行く、というより泥酔したまま運搬されていく体な訳です。いやもおうもない、是非もなし。
嫌いな理由は大体決まっていて、みんな上手くて私が下手なんですね。おまけにみんなメロディー通り歌う。上手い下手は仕方がないし、上手いほうがいいんだけれど、メロディー通り歌うのが気に入らない。同じメロディーだったらオリジナル歌手のCD聴きますよと言いたくなる。おまけに、リフレインの部分なんかでそれまでのメロディーをちょっといじって音が上がったりするところも正式に真似をする。違うところを間違えて上げると、「しまった!」みたいな顔をしている・・・「いやそこは、コードが一緒ですからどこで上げたっていいので、どうぞ良きところで上げてください」と、こっちが気を使ってしまうんですね。で、メロディー通りに歌わなくちゃという「凝り」がこっちに伝染してきてだんだん肩が凝るわけです。人が歌う分にはまだしも、こちらが歌うとなると煩瑣なこと、さらに夥しくなるわけです。適当にメロディーをいじって歌っていると、「この人フシを知らないな」と思った親切な人が自分もマイクを持ってナビゲーションしてくれるんですね。一度面白いことがありました。ある曲を頼んで、そのメロディーの5度上を歌ったらどんな感じになるかと思って歌っていたら、気づいた人がキーを上げてくれる。でも、こっちは5度上を歌っているのでつられて上がって行ってしまい、声がでない。さらに、カラオケマシーンは5度も上がらないので「G坂さん下げて下げて!」などといわれ、相手の気持ちを壊してもいけないと思い、言われるままアロング・ザ・メロディで歌いました(笑)こうやって、使わなくてもいい気を使ったりして疲れるんです。ということで、人が歌っている時はリズムに合わせて踊り、自分が歌う時はジャズ曲を歌うようにしています。踊っていれば凝りは伝染してこないし、ジャズ曲なら他の人が知らないだろうから、のびのびとインチキメロディーで歌えることと、ジャズやっている人ならご存知でしょうが、8ビートよりも4ビートのほうがインプロビゼーションしやすいからです。
そう、このインプロビゼーション(即興)こそ人付き合いの最も重要な要素だと思うのですが、カラオケというのはこれを著しく阻害しているわけです。ぜんぜん即興的じゃないもの。会話で言えば、みんなでシェークスピアのブランクヴァースをなぞりながら対話しているようなもの。シェークスピアならまだしも、今流行のドラマの台詞をなぞって会話しているのと同じじゃないですか?
そういうわけでカラオケには懐疑的なわけです。
ところが、ドラマーと行ったカラオケはどうだったか。徹頭徹尾曲が入らないんですね。もちろんわざとです。歌いたい曲をドラマーが何度入れても違う曲のイントロが流れる。そのたびにドラマーが違うリアクションでこける。
そう、ジャズ好きならやる曲単位のインプロビゼーションを超えて、「カラオケ」、すなわちみんなが曲を順番に入れ(不文律で二度入れを我慢したりしながら)、流れた順に歌い、メロディーは元の歌手をなぞり、ガヤは邪魔にならない様に適度にし、一曲終わるたびにみんなで拍手し云々、という「カラオケ儀式」そのものを題材に彼は即興していたわけです。曲ではなくカラオケをメタな立場からいじって見せたわけです。私たちはそれに即興的に突っ込むことで同じく、「カラオケ」というコードに基づいた即興演奏に参加したわけです。これは滅多なことで成立することではありません。やる側と受け取る側とにスクエアーな連中がいたのでは面倒なことになります。
しかし、この日はドラマーとベーシスト、ピアニストやギタリスト、そしてロープの歌手という錚々たるヒップなメンバーだったので、みな意味を理解してグルーヴ感が醸成され大爆笑のうちに時間が終了しました。こんな面子が揃うことは今後ないでしょうし、そこであそこまでグルーヴすることもないでしょう。ということで、「生涯で一番楽しい」と言い切って差し支えないと思うわけです。