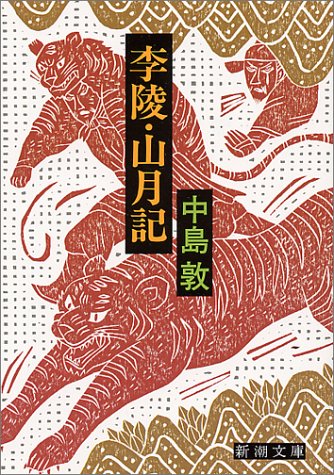中島敦を知ったのは、他の人と全く同じように高校の国語の教科書で「山月記」を読んだ時でした。最初は漢語ばかりで教科書の下段にあった注釈もうるさく非常に取っつきづらそうな印象で、むしろ心に残ったのは章末に載っている中島本人の写真、牛乳瓶の底のような眼鏡が特徴のあの写真でした。しかし、声に出して何度か読んでみると非常に調子がいい。「隴西(ろうさい)の李徴(りちょう)は博学才穎(さいえい)、天宝の末年、若くして名を虎榜(こぼう)に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介(けんかい)、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった」とか「厚かましいお願いだが、、彼らの孤弱を憐れんで、今後とも道塗(どうと)に飢凍(きとう)することのないように計らって戴けるならば、自分にとって、恩倖(おんこう)、これに過ぎたるは莫(な)い」なんていう一節を読むと、その前進的なリズムに魅せられるわけです。
この文庫は中島の作品の中から「山月記」「名人伝」「弟子」「李陵」の4編を選び出した短編集で手軽な一冊です。「山月記」は唐代の李徴が虎になってしまう一種の変身譚が、上にも引用したように漢文学的なリズムと筆致で描かれています。自らが虎に変身してしまうまでの告白には男の生き方について深く考えさせられる思想が、時に漢語、時に撞着語法、時に対句を用いながら説得力をもって語られます。人間であった頃の自分を振り返り、李徴は「己は詩によって名を成そうと思いながら、進んで師に就いたり、求めて詩友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって、また、己は俗物の間に伍することも潔しとしなかった。共に、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心との所為である。己の珠に非ざることを惧れるが故に、敢えて刻苦して磨こうともせず、また、己の珠なるべきを半ば信ずるが故に、碌々とし瓦に伍することも出来なかった」と語ります。この「臆病な自尊心」「尊大な羞恥心」というのは一見オクシモロン(撞着語法)に見えますが、良く考えれば自尊心とは時に臆病さが反転したものであり、羞恥心ゆえに尊大に振る舞う人が多いことも理解できます。そしてこの一編の核心的な一節に至ります。
人間は誰でも猛獣使いであり、その猛獣に当るのが、各人の性情だという。己の場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。
次の「名人伝」は「道」というものの深さを描いたと言えばそうなのかも知れませんし、その背骨にはいわゆる老荘思想があるのかも知れませんが、用いられているイメジからするととても滑稽な話としても読める一編。主人公紀昌は弓の名人になりたくて、飛衛という名人を訪ねると、瞬きをしない訓練を命じられる。すると刻苦勉励してついには目に蜘蛛の巣が張られるまでになる。今度はものを見る訓練を命じられると蚤を飽かず眺め続け、ついには馬ほどにも見えるようになる。こうなると、邪魔なのは師匠飛衛の存在。これを除こうと弓の勝負を持ちかければ、飛衛も我が身が危ないと分かり、弟子の気を他へ転じさせるため、さらなる弓の名人甘蝿老人を紹介し難を避ける。紀昌はこの老師を訪ね、ついには弓の名人中の名人、芸道の深淵を身につけるという話です。なんとなく滑稽感が漂うものの、そこにわずかな皮肉や諷刺もない飄々とした物語が魅力的です。
「弟子」は孔子とその弟子、子路を描いた短編で、一続きの物語というよりも、断片的なエピソードで綴られています。子路は孔子の弟子の中でも特に変わり者だがまっすぐな男で、その心の奥底には単純だけれど深い一つの疑問が横たわっているのです。それはなぜ「邪が栄えて正が虐げられるのか」という疑問です。こういう真っ直ぐな男ですから、師弟の道もまた純粋なもので、「後年の孔子の長い放浪の艱苦を通じて、子路程欣然として従った者は無い。それは、孔子の弟子たることによって仕官の途を求めようとするのでもなく、また滑稽なことに、師の傍に在って己の才徳を磨こうとするのでさえもなかった。死に至るまで変わらなかった・極端に求むるところの無い・純粋な敬愛の情だけが、この男を師の傍に引き留めたのである」と述べられています。この人物像を読むと、私は司馬遼太郎が『項羽と劉邦』の中で描いた平国候候公を思い起こします。彼もまた「食客」に徹して一種の客哲学みたいなものを信奉していた変わり種でした。こうした純粋さは、滅多に見られない徳であるため高く評価されますが、同時に純粋性というものの持つ融通の利かなさが悲劇をもたらします。子路も候公も少し悲しい末路を迎えることになります。いずれにしても「弟子」は「弟子のあり方」について深く考えさせられる作品です。
最後の「李陵」は、武帝の時代に対匈奴最前線に送られ、善戦するも捕らえられてしまい、讒言によって妻子眷属を刑戮された前漢の将軍李陵と、彼を満座の中で弁護したために宮刑に処されるも、その苦難をバネに『史記』を書き上げた司馬遷の物語です。この短編もまた非常に印象深い作品です。李陵が匈奴に下ったという噂が流れ、武帝が激怒するや、その顔色を見た群臣が口々に李陵を罵ります。しかし「今口を極めて李陵を讒誣(ざんぶ)しているのは、数ヶ月前李陵が都を辞する時に盃をあげて、その行を壮んにした連中で」あったし、「漠北からの使者が来て李陵の軍の健在を伝えた時、さすがは名将李広の孫と李陵の孤軍奮闘を讃えたのも又同じ連中で」あったのです。このことに疑問と憤りとを感じた司馬遷は下問を受け、はっきりと李陵を弁護し変節の群臣達を「全躯保妻子の臣(躯(からだ)を全うし妻子を保つの臣)」と罵倒し、このため宮刑(男性の生殖器官を切り取る刑罰)を受けることになります。現代にも、そして私の周りにもこうした群臣のような連中はたまにいます。それまで「立派な人だ、凄い人だ」と褒めちぎっていたにもかかわらず、何かの不運に巻き込まれて、たとえば「哭いて馬謖を斬る」ような目に遭うや掌を返したように、悪口を言い始める連中です。こうした「全躯保妻子の臣」はいつの時代にもいると共に、自ら「私は偽物ですよ、皆さん」と語っているに過ぎないのす。決して信用できない人間であることを自ら告白しているのです。こういう人間には決してなりたくありませんよね。司馬遷への迫害とそれを克服して『史記』を完成させるドラマについては『語らい』の「迫害と人生」でも語られているので、ご存じの方も多いでしょう。
漢語も多いのでなかなか骨の折れる作品ですが、短編という体裁と物語という形式、そして思想に深みがあるので、案外に読みやすくはまりやすい作品集だと思います。また岩波文庫の『山月記・李陵 他九篇』のほうはもっと収録作品が多いので(上の4編に加えて7編)こちらもお薦めです。ぜひ読んで下さい。ところで、冒頭に述べた中島の写真、私はいつも滝廉太郎とイメージがかぶってしまい、いまだに混同し続けているのですが(笑)。