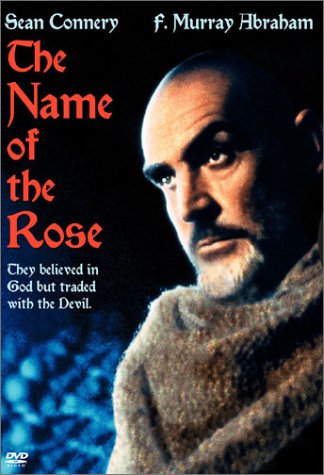When I have seen the hungry ocean gain
Advantage on the kingdom of the shore,
And the firm soil win of the watery main,
Increasing store with loss and loss with store;
--Sonnet 64
(飢えた海洋が陸の王国を侵食し、
こんどは固い大地が大海原に打ち勝ち、
損得が互いに隆替していく様を
私が目にする時に)
ダンのところでも少し触れたが、海による陸の侵食のイメジを用いたシェークスピアの『ソネット』64番からの四行連(quatrain)である。どちらも死を示すイメジとして用いているのであるが、ダンの場合一方的に陸地が海洋によって侵食され減少していく直線的なものであるのに対して、こちらは陸と海とが相争い、互いに勝ったり負けたりしてゆくダイナミズムを含んでいる点で好きである。人生というのは確かに、死を目指してのろのろと這っていくようなものかもしれない。しかしそこには勝ったり負けたりのドラマがあるし、またそのドラマを行き切ってこそ、死の意味を創り出すことが可能になるのではないだろうか?いずれにせよ、人は雨が降るように死んでいくのだから。
この陸と海との戦いはポウプの手に掛かると、縮小化されて才能や性向を示すイメジとしてのんきに用いられるようになる。