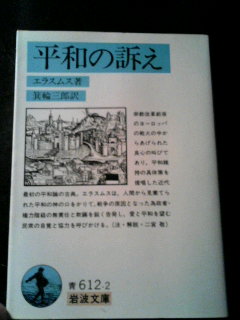高校生の頃『痴愚神礼賛』を読んで以来ずっと感じていたのですが、エラスムスはどこか不真面目な人であるという印象を持っていました。それは扉絵のところに載せられていたホルバイン作の、口元に皮肉な笑みをたたえたこの肖像画から来る印象だけではなく、もっと根源的な不真面目さです。しかも、あまり不快ではない不真面目さ。たとえば同じ諷刺をしてもスイフトなどは生真面目な感じがする。反語を弄しても安吾のほうがずっとまじめだ。それに比べてエラスムスは、これまた随分と不真面目な印象を受けました。しかし、倫理や世界史の教科書にも乗るエラスムスが田舎の高校生に「不真面目だ」の一言で片付けられるような存在であってはおかしい、そんな思いもあって、彼に対してはなんとなくちぐはぐな印象と漠然とした疑念を持っていました。
この疑念が氷解したのは何かの対談集(おそらく、批評空間だったと思います)で柄谷行人が、「真面目の反対は遊びではない、現実だ」と述べているのを読んだときです。私がこれまで「不真面目」だと思い込んでいたことが、実は「現実的」であったわけです。人は遊ぶとき、たとえばチェスをするときルールを無視してポーンを下がらせるような、不真面目なことはしません。そんなことをしたら遊びそのものが崩壊してしまうからです。つまり遊ぶときほど人はルールに対して真面目であるのです。一方現実的であるということは、真面目ではない。ルールに則った戦争などあったでしょうか。公約に真面目な政治などあるでしょうか。もちろん、条約なり公約を守ろうとする姿勢を権力は示しますが、それらは守られないことのほうが多い。しかし人はそれを「現実的な」選択や状況であったとして赦すわけです。
これを混同したらどうなるか?チェスに現実を持ち込んで、上司だから幹部だからポーンが右下に下がってもOKとしたらチェスそのものが崩壊するように、現実をあまりに真面目なルールやロジックで縛れば同じように悲惨な崩壊を引き起こすことになるわけです。それを防ぐためにこそ真面目=遊びと現実の弁別が必要なのです。マキャベリが言ったのもまさにこの点であって、幻想を打ち砕かれたり現実に倦み疲れたインテリをして「現実の政治なんてこんなものさ」と嘯かせるために『君主論』を書いたわけではないことは容易に理解できます。
エラスムスを読むとき聞こえてきた不真面目というペダルノートは、実際はこの現実主義であったのだと思います。エラスムスの伝記を読むと、教会の分裂と相次ぐ戦火の時代に遭遇し、教会の分裂という事態を何とか回避ようと試みながら、はからずもルター派と反ルター派の両方から批判され、国王たちににもその名声を利用されながら、彼らの逆手を取って自らの平和思想を公にする機会を得ていく、そんなタフで現実的な姿がうかがえるのです。幼い私はそれを、不真面目であると読み間違えていた。そしてこの現実主義と不真面目との混同を払拭すると、そこに見えてくるのはエラスムスの強烈な理想主義、しかも現実に耐えそれを乗り越えようとする希望に満ちた理想主義なのです。
そんな理想主義者のエラスムスは『平和の訴え』でこう述べています。
君主たちは自分のためにではなく、民衆のためにこそ英明であるべきです。また君主は、自分の威厳や幸福、力や栄光を、君主を真に偉大かつ抜群たらしめる事績によって測るだけの名識を備えているべきです・・・・こうして国王は、最良の人民を統治するときに自らを偉大と考え、人民を幸福にしたとき初めて自らを幸福と考えるべきです。また国王は、完全に自由な人間を支配する場合こそ真に高貴なのであり、人民が富裕になって始めて自らも富裕なのであり、諸都市が恒久平和に恵まれ繁栄する時、始めて己も繁栄するものと考えるべきです。(49節)
この一節に、皮肉なエラスムス像を読み込むのも、非現実的な理想主義を読み込むのも自由ですが、それは読む側の気持ちの反映なのであって、エラスムスの問題ではないわけです。現実主義を標榜する政治学者たちがイロニッシュな御用学者となってしまったり、反対にあまりに現実とかけ離れた理屈を整然と展開し(現実という変数を捨象すればたいていのことは整然となりますが)現実を見くだした姿勢をとるのは、どちらも理想と現実という、永遠に和解することのない二重性の重荷に耐え切れなくなって、前者は幻滅し後者は逃避しているのだと私は思います。
国家間、民族間の対立と反目についても簡潔な筆致で、
イングランド人はフランス人を敵視していますが、その理由はといえば、それはただフランス人であるということのほかは何もないのです。イングランド人はスコットランド人に対し、ただスコットランド人であるというだけのことで敵意をいだいているのです。同じように、ドイツ人はフランス人とそりが合わず、スペイン人はこれまたドイツ人ともフランス人とも意見が合いません・・・・名前のような取るにたりない事がらが、かずかずの自然の結びつきやかずかずのキリストの絆より一そう強い力をふるうとは、どういうことでしょう?(59節)
と、その愚かで無根拠な本質を暴きます。
そして、平和への方途を民衆の自覚へと向けていきます。
キリスト教徒の名に誇りをもつすべての人びとよ、心を一つに合わせて戦争に反対の狼煙をあげてください。民衆の協力が専制的な権力に対してどこまで抵抗する力があるかを示してください。この目的のために各人はそのすべての知恵を持ち寄っていただきたいのです。(74節)
大多数の一般民衆は、戦争を憎み、平和を悲願しています。ただ、民衆の不幸の上に呪われた栄耀栄華を貪るほんの僅かな連中だけが戦争を望んでいるにすぎません。こういう、一握りの邪悪なご連中のほうが、善良な全体の意志よりも優位を占めてしまうということが、果たして正当なものかどうか、皆さん自身でとくと判断していただきたいもの・・・・戦争は戦争を生み、復讐は復讐を招き寄せます。ところが、好意は好意を生み、善行は善行を招くものなのです。(76節)
表紙解説
宗教改革前夜のヨーロッパの戦火の中からあげられた良心の叫びであり、平和維持の具体策を提唱した近代最初の平和論の古典。エラスムスは、人間から見棄てられた平和の神の口をかりて、戦争の原因となった為政者・権力階級の無責任と欺瞞を鋭く告発し、愛と平和を望む民衆の自覚と協力を呼びかける。